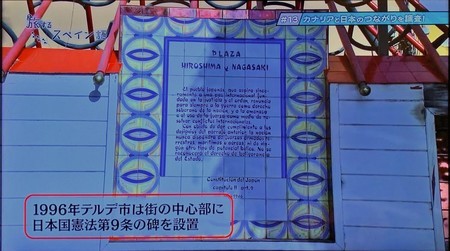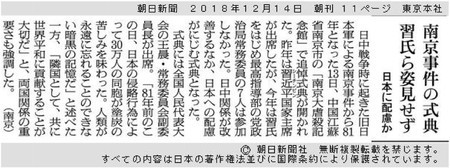-共同通信 2019年1月27日 「長崎市、韓国で被爆者手帳を交付」 http://archive.fo/GKlR4
去る8日の長崎地裁の判決に基づき、韓国人被爆者に対して長崎市が韓国で被爆者健康手帳を交付した、というニュースです。最初から交付すべきだったとは思うものの、控訴しなかったのは高齢の当事者のためにはよかったと言えます。
今回の訴訟の前提の一つをなしているのが、2008年に成立した改正被爆者援護法です。孫振斗裁判での日本政府の敗訴(1974年)をうけて韓国人被爆者への援護がようやく始まりますが、厚生省(当時)は被爆者手帳が国内でのみ有効であるとする通達を出し、韓国在住の韓国人被爆者への援護をネグってきました。2008年の法改正でようやく海外から被爆者手帳の交付を申請できるようになったわけです。
ところで韓国人被爆者の裁判闘争は、戦後補償裁判のなかでも原告勝利の判決がたびたび下されて確定しているという点で異彩を放っています。私は各訴訟について詳しく判決文を検討したわけではありませんが、原爆による被害の場合特別な立法による救済が行われてきたことがどうもその背景にあるようです。
例えば2008年の法改正に先立ち、海外在住の被爆者にも被爆者援護法上の「被爆者」の地位を認めた判決(郭貴勲裁判)が2001年に下っていますが、その確定判決(大阪高裁)は次のように判断しています(郭貴勲裁判 高裁判決全文)。
(……)被爆者援護法の複合的な性格、とりわけ、同法が被爆者が被った特殊の被害にかんがみ、一定の要件を満たせば、「被爆者」の国籍も資力も問うことなく一律に援護を講じるという人道的目的の立法であることにも照らすならば、その社会保障的性質のゆえをもって、わが国に居住も現在もしていない者への適用を当然に排除するという解釈を導くことは困難である。
被爆者援護法があるがゆえに国家無答責、除斥期間、日韓請求権協定等々、戦後補償裁判で原告の請求を阻んできた論点での争いにならず、裁判所としても原告勝利の判決を書きやすかったのではないか、と。