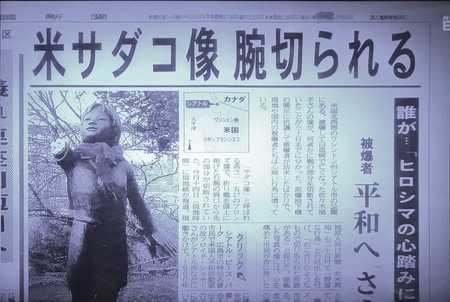元朝日新聞記者の植村隆氏が櫻井よしこ氏を訴えていた民事訴訟の判決が、去る11月9日に札幌地裁で言い渡されました。結果はみなさんご承知の通りで植村氏の請求が棄却されましたが、一審の結果がどうであれ実質的な決着の場が札幌高裁になるであろうことは、双方の当事者や支援者にとっても織り込み済みだったと思います。
すでに原告は控訴する旨を公表していますが、ここでは原告植村氏の支援グループが公開している判決要旨に基づいて、地裁判決について当ブログの見解を述べておきたいと思います。
判決要旨のうち、実質的に勝敗を分けることになった部分は「3摘示事実及び意見ないし論評の前提事実の真実性又は真実相当性」です。裁判所の判断については判決要旨をご覧いただくとして、植村氏に関する櫻井氏の記述の真実相当性を判断するうえで非常に重要な事実として、彼女が日本軍「慰安婦」問題について公に発言するようになったのは1996年以降である、というものがあります。1990年から91年にかけて取材し記事を書いた植村氏とは異なり、櫻井氏は92年に刊行された資料集(大月書店)や95年に刊行された吉見義明さんの『従軍慰安婦』(岩波新書)などの調査・研究の成果を参照できたし、また参照すべきだったのです。近年まで続いていた植村氏への攻撃については、過去四半世紀の研究の蓄積をふまえたうえでなされたのでなければ、真実相当性があったと認めることはできないはずです。
しかし判決要旨を見る限り、裁判所は植村氏の記事が掲載された時期に入手可能だった資料のみをとりあげ、それをもってして「……と信じたことについて相当な理由があるといえる」という判断を下してしまっているように思えます。
もう一つ、植村氏の義母が「遺族会」の幹部であったという事情も真実相当性を認める根拠の一つとされています。しかし櫻井氏は、特に公知の事実というわけでもなかった植村氏の縁戚関係には注目する一方、植村氏の91年8月の記事が執筆・掲載された時点では金学順さんを支援していたのが挺対協(当時、現「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」)であって「遺族会」ではなかったこと、12月の記事が掲載されたのはすでに提訴のあとで各社とも植村氏の記事とさして違いのない記事を掲載していたこと、さらに12月の記事が掲載されたのは大阪本社版だけであること……などの、より明白な事実を無視ないし軽視していたわけです。これでなぜ「……と信じたとしても、そのことについては相当な理由がある」などと言えるのか、非常に疑問に思います。